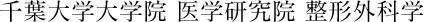英国留学記 ー Performing Arts Medicine UCL, 金塚彩 ー
更新日 2017.10.11
現在英国University College London(UCL)大学院に入学し、Master CourseでPerforming Arts Medicineを学んでおります。私は日本ではまだあまり知られていない分野に興味があり、国内では体系的に学ぶことが不可能であるため留学することにしました。研究室や病院ではなく、大学院に入学するという形で留学しており、少し珍しいケースかもしれませんので、近況報告を兼ねて留学に至る経緯について書くことにしました。長文になってしまい読みづらい所もあるかもしれませんが、どうかご容赦下さい。まだ留学の途中なので続きはまた別の機会にお伝えいたします。
《1.》Performing Arts Medicineとは
Performing Arts Medicineとは、ピアニストやバイオリニスト、パーカッショニストなどの楽器演奏者、オペラ歌手やポップミュージックの声楽家、バレエ団やサーカス団などのダンサー、パフォーマーの診療、研究に関する医学です。スポーツ医学がアスリートや運動愛好家を対象に発展してきたことを考えて戴くとイメージしやすいと思います。演奏家、声楽家、ダンサーにとってけがや痛みのケア、リハビリテーション、声のマネージメント、舞台恐怖症の対策はたいへん重要です。Performing Arts Medicineの知識、経験がある医師、看護師、PT、OT、ST、臨床心理士などから構成されるチームによる診療が理想的であり、そのシステム構築は急務と考えられます。具体的な診療科としては、整形外科、神経内科、耳鼻科、総合診療科、産婦人科、精神科、リハビリテーション科などがあげられます。Performing Arts Medicineはアメリカ、イギリス、ドイツ、オーストラリアなどで発達してきましたが、残念なことに我が国ではまだ医療スタッフが学べる教育機関はなく、クリニックもわずかにしかありません。
私自身、昔スキー中転倒して右前腕骨骨折を受傷してしまった際、同時期にオーケストラでコンサートミストレスを務めていたため、仲間に大変な迷惑をかけてしまった苦い経験がありました。若かったとはいえ自覚不足で申し訳ないのと同時に、演奏に支障が残らないかどうか怯える日々を送ったことがあり、この分野に強い関心を寄せるようになりました。芸術系のPerformerのみなさまが安心して活動を継続できるよう、そのサポートが少しでも出来ればと思い、それが情熱の源です。
《2.》音楽家の手をみるということ
さて私がこの分野を目指すことにした理由は、自身がけがをしたことともう一つ、研修医時代に岩倉菜穂子先生が下さったDr. Ian Winspur著の 「The Musician’s Hand: A Clinical Guide」という教科書との出会いが動機となりました。この本は、音楽家のけがや変性疾患の有病率や治療指針、楽器特異性に沿った治療指針のTips、手術症例の紹介、舞台恐怖症と薬物治療の選択肢など、音楽家に関わる医学的問題がまとめられた良著です。
しかし入局して痛感し続けたのは、整形外科医を名乗るのに必要な知識と経験の圧倒的な量でした。六角智之先生のもとで研修した時には、手外科医をやりたいなら解剖に精通して外傷の手術が一通り出来なければ到底だめだと教わりました。基本的なことが出来て初めて次のステップに進まなければならない、そして新しい分野を開拓するには相応の覚悟が必要だとも指導されました。臨床に四苦八苦するたび、六角先生の言葉の重さをかみしめていました。これからも精進しなければいけないと感じています。
《3.》留学する決断
今となっては当初から留学する気満々だったように見えるかもしれませんが、研修中は臨床に精一杯でほとんど考える気力がなく、忘れていました。しかし思い返せば高校生の時から海外留学をしたいとずっと考えていたのです。英語が好きということの他に、知らない世界への好奇心、一流・ほんものとはなにかを知りたいという渇望が根底にあったように思います。2014年の帰局1年目の年度末、助川浩士先生が卒後米国ClevelandのMayo Clinicに留学されるのを見送るとき、自分も留学したい、したかったのだという気持ちがこみ上げてきました。それから、実は留学したいんですよねとぽつりぽつりと口に出すようになり、先輩方からもそういう気持ちがあるならぜひ頑張ってと言われるようになりました。
《4.》留学先選び
そうだ留学しようと思ったものの、どこに留学するかという問題がありました。英国UCLへの留学に至るまでには、長く先の見えない紆余曲折がありました。
(1) 米 Mayo Clinic
Mayo Clinicは言わずと知れた世界の名門病院です。私がこの病院の名前を知ったのは、医学部に入学したての頃でした。当初医学書を探しに本屋さんに行ったのですが、知識がなさすぎて選ぶことができず、医学書のとなりに陳列してあったHelen Clapesattle著の「The Doctors Mayo」という本を買いました。当時Mayoのメの字も知らなかった気がしますが、米国北西部の一地方都市で医療を発展させ巨大医療施設を築き上げた創設者とその2人の息子兄弟の話は、西部開拓のようで夢があり心を躍らせて読んだのを覚えています。
助川先生が去られた後、私もMayo Clinicに留学してはどうかというお話が出るようになり、留学の可能性が現実味を帯び始めました。Mayoの研究実務のみならず家、車などを代々引き継いでいるとのことで、そのリレーのたすきを担う事が出来たら、と考えました。しかしMayoで引き継がれていた研究内容はバイオメカ領域であり、私の当時始めていた研究が解剖学的検討であったので、テーマの変更か追加か、いずれにしても舵を切らなければなりません。さらに留学を生活の面から考えると、ロチェスターの冬は雪深く車が必須になりそうなこと、趣味の音楽・ミュージカル鑑賞や美術館巡りがあまりさかんにやれなさそうなことなども気になりました。行ってしまえば楽しい、そう思いながらも、この貴重な機会を最大限活かすためにも慎重に留学先を選ばなければと逡巡していました。
(2) 英 Oxford University
2014年度末から、猛烈に留学先の情報を検索し始めました。留学費用のことも考え、奨学金や助成金の面からもアプローチしました。相当な時間を留学先と助成金の検索に費やしました。公募期間や資格など虱潰しに調べて片っ端から応募し始めました。中でもOxford University(整形外科)への留学助成金には真剣に取り組みました。提出書類も英語が使われるので、前教授の高橋和久先生にはお忙しい中、添削をして戴きとてもお世話になりました。2015年12月、分厚い応募書類を準備して臨みましたが英語のIELTS (International English language test system) 7.5の壁が超えられず断念しました。しかしながら自分の研究内容、動機、展望を文章化する過程で自分が何をやりたいのかが徐々に明確となり、様々な方からの助言を戴くことができたので無駄ではなかったと思います。
(3) 独 Berlin’s Center for Musicians’ Medicine, Charite - University Medicine Berlin
2014年度末から2016年初頭まで環境生命医学教室にお世話になり学生の肉眼解剖実習の指導にあたっていた頃、ドイツのCharite University Medicine Berlinに音楽家のための専門センターがあるという情報を得て、留学の交渉に訪れることにしました。2015年秋、社会医学教授でWorld Doctors Oechestra 指揮者のProf. Stefan Willichとお会いし、自己紹介と日本の現状を説明してぜひセンターを見学したいと伝えると、その場でぜひどうぞ快諾して下さいました。2016年春、神経内科医でピアニストのセンター長のProf. Alexander Schmidtのもとに留学しました。Schmidt教授はHanns Eisler音楽大学で講座をお持ちなので、音大にも通いました。夢のように素晴らしいシステムが確立しており大変勉強になりましたが、長期の留学先という視点で考えると、どうしてもドイツ語(と英語)がネックになると感じました。言語の習熟度によって得られる情報量は変わりますし、直接読み、書き、話せる喜びには何にも代えがたいものがあります。欲張りかも知れませんが、せっかく留学するなら英語力も上げたい。となると英語が母国語の国がベストだろうと判断しました。フランスのDr. Raoul Tubianaのクリニックも検討しましたが、同じ理由で他の選択肢に目を移すことにしました。
(4) 英 Performing Arts Medicine, University College London (UCL)
時期が前後しますが、2015年春、第58回日本手外科学会学術集会で「The Musician’s Hand: A Clinical Guide」の著者のDr. Ian Winspurが来日しました。運命的な出来事でした。連絡先を交換し、クリニックへの留学の打診をしたところぜひどうぞと言って戴きました。その後のemailのやりとりの中で、UCLの大学院でコースを持っているから入学してみたらと提案されました。確かに、クリニック留学は魅力的ですが、私の場合新しい分野を学ぶので、臨床の合間に教わると知識が断片的になるかもしれないと懸念し、より体系的に学べる上に同じ志を持つ仲間が出来る大学院入学を視野に入れることにしました。
UCLの合格条件の一つにIELTSのスコアがあり、結果的に日本で7回、ロンドンで1回受験しました。働きながら、博士論文のための研究をし、週末British CouncilのIELTS対策コースに通う日々が続きました。5回目の受験の結果がだめだと分かったとき、さすがに途方に暮れました。Dr. Ian WinspurからUCLのProgram Lead、整形外科医でピアニストの女性医師、Dr. Hara Trouliを紹介して戴いていたので、emailで事情を説明して、2016年11月ロンドンでお会いするアポイントメントを取り付けました。Dr. Haraは笑顔が印象的な、優しく親切で有能な方でした。渡英しUCLの彼女のオフィスで面談をし、色々なお話をしました。しかしUCLは大学入学資格に非常に厳格であり、その裁量権は大学に帰属しているため個別の対応は難しいとのことでした。英語の壁は思った以上に深刻なものでした。博士課程の研究をして別のテーマで卒論を書きながらこのハードルを果たして乗り越えられるのか自信はありませんでしたが、とにかくやるしかないと心に決めていました。
英国の大学院受験は、First come, First Served、すなわち席は早い者勝ちであるため、応募が始まって間もなくapplyを完了させなければなりませんでした。何から何まで英語なので本当に苦しかったです。CV letter、Personal Statement、Recommendation Letterは、これまで助成金の申請で推敲を繰り返し書いたものを役立てました。そして学費の問題もありました。UCLはOversea studentsにはEUの学生の2倍の学費を課しています。これだけでもかなりの額ですが、留学準備費や渡航費用、生活費を含めると相当の出費が見込まれたので、助成金、奨学金への応募を続けました。応募するために自分の研究について日本語、英語で大量の書類を作成しました。面接審査が英語のところもありました。申請の際にはまだ留学先が確約していなかったので、暗中模索の状況でしたが、どうしても音楽家の支えになりたいという情熱をアピールし続け、2016年冬、吉田育英会と経団連から合格の知らせが届きました。自分の夢の背中を押して戴き、感謝の言葉しかありません。様々な出会いに恵まれ、人生のヒントもたくさん戴いた気がします。
そうこうしているうちに、IELTSのスコア以外を無事クリアし、2016年12月UCLからConditional Offerの知らせを受けました。Conditional Offerとは条件付き合格のことで、2017年9月までにIELTSで7.0をクリアするか、UCLのPre-sessional English Courseを受講して試験に合格すれば、入学を許可するというものです。一応Offerを得たことで安堵しましたが、英語の壁はなおも立ちはだかり、不安を抱えたままの渡英となりました。
《5.》ロンドンでの生活
渡英直後はロンドンの街並みに心躍り、わくわくしながら生活が始まりました。町中を歩くたび感じるのは、ロンドンはMulti-cultural City(多文化都市)だということです。白人の方の方が少ないです。私の住むロンドン西部のエリアにはインド人やポーランド人がたくさん住んでいます。大学のある中心部にいたってはほとんどの国籍の人がいるのではないかというくらいのものです。飛び交う言葉も英語ではないし、お店のスタッフの英語も自国訛りでうまく聞き取れず、ガスや水道会社に電話するときなどは特に苦戦しました。国籍も宗教も性別も色々、服のセンスもそれぞれなのでファッショントレンドなんてあってないようなものです。一人一人が違う、違って当たり前、という雰囲気に、日本人である私もここにいることが許されている、というかむしろ誰も気にもとめてもいない感じが逆に心地よく、ストレスが少ないです。
私の家は、大きな家の中で8軒程度の家族が居住するパーパスビルトフラットと呼ばれるものです。物件探しの際の条件は、交通の便と治安の良さ、門があること、バスタブがあること、ゲストルームがある2階以上の家具付きであること、でした。ロンドンの物価は恐ろしく高く、そしてバスタブがある物件は少ないのでかなり調べて選びました。結果、駅から少し離れていますが、私立のPrep Schoolが近くにある緑豊かなお庭付きの今の家になりました。庭にはリスやキツネが遊びに来て、窓からはこどもたちがスポーツする様子が眺められるこの家は、本当にお気に入りです。とはいえ生活が落ち着くまでは色々ありました。急にお湯が全く出なくなり家主や修理工が7回家にやってきたり、キッチンが壊れたり、部屋でクモが産卵したり、配管が床の下で壊れて水漏れしたり、色々ありました。そのたびにギリシャ人の家主や修理工とやりあうのですが、対応がたまにものすごくいい加減だったので何度かバトルしました。こういった洗礼を受けて外国で生活するってこういうことなんだと学びましたし、しっかり意見を言わないと(時に言ってもやらない)生きていけないと分かりました。
そして食事。イギリスはまずいとよく言われますが、イギリス人と話すと、昔と比べたらすごく美味しい、うまいイギリス料理を知って欲しいと言います。しかし残念ながら私には味付けが合いません。土鍋を日本から持参して毎日お米を炊いて和食を食べています。またこちらのPubは日本のパブの意味と違って、子供から老人がやってくるレストラン兼バーのようなところで、種類豊富なクラフトビールが楽しめますが、日本人の感覚からするとぬるめで出てくるので、結局キンキンに冷えたアサヒスーパードライの方がしっくり来てしまいます。
テロについて少しだけ触れます。2017年現時点までですでに4回のテロがありました。身近な場所で発生しており恐ろしいですが、生活しなければなりません。閉鎖空間である地下鉄に乗るときなどはいつもどうかテロが起きませんようにと思います。無事に帰国するまで気を緩めず過ごそうと思います。また強いて言えばスリに遭う確率の方が高いので、家の外にいるときはいつも多少の緊張感を持って過ごしています。私の友達の3人は最初の数ヶ月でiPhoneを盗まれました。物乞いも街のあちこちにいるので、貧富の差や難民の存在を日常的に感じます。
《6.》UCLのPre-Sessional English Course
先ほど書いたように、私はConditional Offer(条件付き合格)の状態で渡英しました。日本を発つ直前のIELTSでも惨敗でした。ひょっとしたらUCLに合格できないかもしれない、そしたら一体私は何しに英国に来たのだろうと考えると、憂鬱を通り越して恐怖でした。イギリス人の家庭教師の先生についてもらい、Pre-Sessional Courseが始まるまでひたすら机にかじりついてIELTS対策をする日々でした。そして2017年5月、ロンドンで受験したIELTS。私はついにハードルを越えたのでした。結果が分かったときには嬉しくて涙が出ました。様々な人に支えられてどうにかスタート地点につけたと思うと、感動はひとしおでした。そして念願のUnconditional Offer(無条件合格)を手に入れた状態で、Pre-Sessional English Courseが始まりました。
UCLのPre-Sessional English Courseは、主にMaster Courseを目指す、非英語圏からの留学生を対象とするAcademic Englishのコースです。Academic Style、Critical Thinking、Presentation Skillを主な柱として学びました。全体の学生数は200名程度ですが、1クラスの平均は15名程度のSmall Groupで良かったです。私のクラスはサウジアラビア人1人、イラン人1人、タイ人1人、韓国人1人、日本人1人(私)、他中国人8人という構成で、圧倒的な中華パワーを感じて過ごしました。毎日の授業と課題が大量だったので必死でした。私はUnconditional Offer Holderだったので最終日のReading/Listening/WritingのPaper testは免除になりましたが、2000 wordsのAcademic Essayと15分のPresentationはやりました。努力のかいがあり評価は全てExcellentでした。英語の読み書き話す、どの要素についても非常にしっかりとしたFeedbackがあり、参加して良かったです。特にSpeakingでは、TED.comをたくさん視聴することが勧められただけあって、Interactiveな姿勢で自信を持って話すという訓練を受けました。医学部で特にスピーチの訓練は受けなかったので良い機会でした。
《7.》Division of Surgery and Interventional Science, Performing Arts Medicine, UCL
UCLのPerforming Arts MedicineはDivision of Surgery and Interventional ScienceのMaster Degreeのひとつとして2011年に発足しました。包括的教育カリキュラムのもとでPerformerの診療、研究の専門家を育成し、修士号を授与します。受講者は自身の音楽やダンス経験を医学に昇華させ、トップレベルのPerformerの健康問題を正しく評価し適切に対応できるになることを目指します。卒業生は病院や専門クリニック、音楽・ダンス学校、オーケストラやダンスカンパニーにおいてキャリアが継続できるようバックアップされます。なお、Institute of Sport, Exercise and Health (ISEH)、Royal National Throat Nose & Ear Hospital (RNTNE)の協力を得ており、スポーツ医学分野とのコラボレーションや病院見学のチャンスがあります。講義内容は大きく8つの分野で構成されており、各々2時間の筆記試験、口頭試問、20分のPresentation、OSCEs(Objective Structured Clinical Examinations)、2000 wordsのEssayによって評価されます。これらの座学に加えてクリニックでの実習、プロフェッショナルのPerformerや学生を対象とした研究を行います。
なんと留学生は私しかおらず、残りは全員イギリス人の医師やPT、OTの方で、年齢は20代から50代と幅広いです。他にも海外からのConditional Offer Holderが数名いたのですが、英語のスコアが足りなかったということです。私はPre-Sessional English Courseを終えてからも英語の勉強を続けていますが、現地人の日常会話についていくのはかなり厳しいです。現在は、Musculoskeletal and Neuromuscular Injury、Environmental & Lifestyle issues、Clinical Management of the Professional Voice User、Research Methodologyの講義と実習に参加していますが、当然講師の先生もNativeなので怒濤のような英語に悪戦苦闘しています。幸いProgram LeadのDr. Haraが、必ず授業の前に授業のスライドや参考文献をUploadしてくれるので、事前に英単語を調べてから臨むようにしています。待ち焦がれていたこのチャンスを最大限に活かして、たくさんのことを吸収して帰りたいと思っております。音楽家の診療はInterdiciplinarity、すなわち様々な分野の専門家との協力なしには成立しません。学んだことは形にして発信し、少しでも多くの仲間とともに発展させていけたらと思っております。
《8.》おわりに
現在無事に留学生活を送れているのは、日頃サポートして下さった方々のおかげだと思っております。研修中、そして大学でお世話になった先生方、手外科グループの先生方、同期の仲間や先輩、後輩のみなさまの叱咤激励に感謝しております。いつもおおらかに見守って下さる國吉一樹先生、鈴木崇根先生、松浦佑介先生のもとで大学院生活を送れたことは人生の転機でした。常に知恵を授け応援して下さった高橋和久先生、大鳥精司先生、ありがとうございました。そしてどんなときも味方でいてくれる家族がいてくれるからこそ前だけを向いて走ることができました。これから様々な困難があるかもしれませんが、悔いの無いように過ごしたいと思います。今やっとスタートラインにたったところなので、これから頑張ろうと思います。今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。