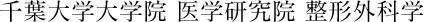第45回国際頚椎学会 (CSRS)に参加して
更新日 2017.12.8
要旨
- 一時のBig data解析のブームは落ち着き、通常の症例対照研究に回帰していた。
- 単施設データの発表は少なく、多施設共同研究が多くを占めていた。
- コホート研究や前向き比較対照研究は注目される。
- 欧米と本邦では手術対象患者や手術適応が違うことを理解する必要がある。
- 単に欧米に迎合するのではなく、欧米の良い部分は取り入れつつ、引き続き神経症候学を大切にする日本の丁寧な診療の強みを生かして日本人及びアジア人に適した我々の治療ストラテジーを考えていくことが大切である。
はじめに
2017年11月30日から12月2日の日程にて米国Florida州Hollywoodで開催された国際頚椎学会 (Cervical Spine Research Society, CSRS)の45th Annual meetingに参加した (図1, 2)。応募演題数430題余、口演採択81題、ポスター採択60題 (口演採択率18%、口演とポスターを合わせた採択率32%)であった。以前に比べると採択率は少し上昇したものの、口演での採択は依然狭き門である。千葉大からは大学院生4名と私が演題応募したが、残念ながら今回は私のポスター1題のみの採択であった。私はK-line (-)例の頚椎後縦靭帯骨化症に対する後方除圧固定術の5年成績を発表した。ポスター発表はon site standingやpresentationが無かったため、学会全期間を通じリラックスして他の演者の発表を聞くことができた。同門からの参加は國府田正雄先生 (H3卒)と私の2名であった (図3)。國府田先生は昨年度の21st century research and education grantsを受賞されており(脊髄損傷後急性期の新規バイオマーカーの探索に関する研究で、大田光俊先生 (H18卒)の学位研究テーマ)、その研究内容についての報告発表があった (図4)。
学会の動向と今後の研究手法の在り方
本学会は最近数年の傾向として、FDAや州の保健衛生局が収集しているBig dataを用いたCost effectivenessやQOL (Quality of Life)評価に関する発表が多くみられていた。しかしながら今年の学会における発表は、現場の詳細なデータを解析した古典的なスタイルの症例対照研究が多くを占めた。内容としても外科医が本来議論すべき手術成績や合併症、術式の工夫に関する発表が多かった。今回の学会は本来の外科系の臨床の学会のあるべき姿に戻ってきた印象を受けた。もちろん医療費の問題は重要であるが、ここ数年のBig dataを用いた研究でその結果や方向性はある程度見えており、そういった研究への現時点での答えは出たのであろう。また、真の医療の目的は患者のADL (Activities of Daily Living)改善および、その先にあるQOL改善であることは疑いの余地はない。研究の主要評価項目としてQOL指標、QALY (Quality adjusted life year)やCQLY (cost / quality life year)等を設定することも、それが可能ならば大変よい研究手法であると考える。ただ、今年の学会ではQOL評価に関する発表についても、サンプル数10万例といったデータからではなく、自らのチームが関わった (ある程度背景を揃えた)数十~数百といった規模のデータにて検討するという、従来の研究手法に戻っている印象を受けた。
印象的であったのは、単一施設のデータによる発表は少なく、多くはMulti-center studyであった。本邦からの発表も、口演採択演題はレジストリを利用した多施設共同研究や住民コホート研究が多かった。科学的に (この場合、=統計学的に)エビデンスのある結果を出すにはある程度の症例数が必要である。単一施設での解析ではなく、多施設研究を積極的に進める必要がある。そのためには本年4月より本格的に稼働した千葉レジストリデータの有効活用や、登録施設間における多施設共同前向き研究が期待される。その際には雑多な集団で検討するのではなく、ある程度研究への組み入れ基準・除外基準を明確にして精錬されたデザインの研究が求められている。加えて欧米からも前向き研究はまだまだ少ないので、多施設前向き比較対照研究や、倫理的に可能な分野であればランダム化比較対照試験が理想的な研究である。本邦では臨床研究に関する法整備が進む中で、侵襲性を伴う前向き臨床研究の敷居が高くなりつつあるが、法律に準拠しつつ積極的に前向き研究も推し進めていかねばならない。
米国の頚椎手術の現状と我々が彼らから学ぶもの
この学会に参加すると、ひとえに頚椎の外科的治療と言っても、国や地域によって手術適応や治療ストラテジーが大きく異なるということがよく分かる。手術対象疾患群を (1)radiculopathy、(2)cervical deformity、(3)myelopathyの3つに大別してみる。(1)はradiculopathyや、時にneck painに対し頚椎前方椎間板亜全摘術 (Anterior cervical discectomy and fusion; ACDF)、頚椎人工椎間板(cervical Total disc replacement; TDR)や椎間孔拡大術を行うものである。(2)は各種 deformityに対しインストゥルメンテーション固定や骨切りのテクニックを用いたアライメント矯正を施行するものである。(3)は頚椎症性脊髄症や頚椎後縦靭帯骨化症に代表されるような疾患の進行したmyelopathyに対する除圧 (固定)手術である。 ちなみに、話は少し脇道にそれるが、ACDFは米国で年間13万件施行されており、周術期の医療費は1件平均18,000ドル、平均入院期間は1.7日、1・2椎間については多くの施設にて日帰り手術を行っているとのことであった。
この3つの疾患群でいうならば、日本人の脊椎外科医の多くが手術対象として捉えている主たる疾患群は(3)のmyelopathyであり、時に保存療法抵抗性の (1)radiculopathyの手術とシビアな (3)deformityも行っている、という割合が一般的であろう。
しかしながら米国では多くは(1)のradiculopathyやneck painに対する手術治療が大きな割合を占めているようである。もとも骨格の大きなアジア系以外の欧米人は有効脊柱管径が広く、developmental canal stenosisを呈しておらず、myelopathyの患者は少ない。また、保険制度の違いや文化・生活習慣の違い、患者のarm pain, neck painに対する考え方に違いもあると思われる。このように手術対象疾患患者の違い、手術適応の考え方の違いが根本にあるため、欧米人の発表趣旨がなかなか理解できなかったり、討論において相互理解が進まないことがある。
また、他国の発表では神経症候学よりも画像診断学に重きを置き、安易に除圧範囲や固定範囲を広げたり、我々からみると不必要な固定術を行っていることも多いと感じた。手術成績に関する発表は多いが、神経症候学や診断学に関する発表はほとんどない。手術成績に関する発表においても組み入れ基準が曖昧で、治療対象や治療ゴールが異なる疾患が混ざっている研究がある。例えば「Cervical deformityの治療成績」「1椎間ACDFの治療成績」と題して、radicular painの患者とneck painの患者とmyelopathyの患者を一括に論じている発表がみられた。併せて、neck painに対する固定術が受け入れられていることや、neck painに対しその原因を矢状面バランス異常に求め、後弯矯正固定手術が行われていることは、我々の考え方とは大きく異なる。
このように我々日本の脊椎脊髄外科学は、欧米と比較し、手術対象とする疾患群のポピュレーションがそもそも違うということ、手術適応のストラテジーの立て方が違うこと、この2点をまず理解した上で彼らの発表から学び、良さそうな点を取り入れるのがよいと思われる。興味深いことに、ごく軽度の頚椎後弯症例に対する矯正固定術を是とする米国からの発表に対し、別の米国人から手術適応及び結果の解釈に対して懐疑的な質問や批判的なコメントがあった。米国にも日本人脊椎外科医の意見に近い考えを持つ方もいるようである。
以下、私が聴講し得た学会初日、2日目の全口演の中で、個人的に興味を持った発表についていくつか紹介する。
- 頚椎人工椎間板 (TDR):5-7年成績が報告されていた。SwedenのOlerudのグループから当該椎間の椎間関節のOAの進行に関する発表があった。他はTDRのACDFに対する同等性 (治療成績、Cost value、QOL)と優越性 (隣接椎間障害)に関する発表が多かった。
- Cervical deformity:Cervical deformityに対する手術における基準値や目標値はまだ手探りのようである。腰椎のPI (Pelvic Incidence)とLL (Lumber Lordosis)の関係式を参考に、Th1 slopeとCL (Cervical Lordosis)に理想のCL値の算出の突破口を見出そうとする発表がいくつかあった。New YorkのPassias、San FranciscoのAmesらがInternational Spine Study Groupとして多施設共同研究のデータを様々の切り口から多数発表していて他を圧倒していた。また、(手術台の傾きを変えても)術中に測定可能な新たなパラメータとして、C2-Th1 tiltが提案され注目されていた。
- 米国より脊椎手術に関連した医療裁判に関する報告があり、興味深く聴講した。裁判の争点は1位:Technical / Judgement complaints、2位:Nerve injury (Spinal cord 48%, Peripheral nerve 34%)、3位:Informed consent、4位:Wrong level surgery、5位:Foreign body !?であった。特にInformed consentが係争原因の上位に入っていたが、患者医師コミュニケーションの在り方次第で予防可能なものであるとして強調されていた。
- 画像診断で、頚髄症発症のStart pointを探る研究がTorontoのFehlingのチームより発表されていた。当グループも現在牧聡先生、北村充広先生を中心に取り組んでいるSpinal Cord Tool Boxを利用したMRI Diffusion Tensor Imagingに関する研究と、MRI T2 Star強調画像を用いた手法に関する内容であった。
- メーカーセッション (ランチョンセミナー)では日本でもようやく臨床使用が可能となった頚椎人工椎間板 (TDR)に関する発表を聴講した (Medtronic社、Prestige LP)。既に欧米は7年の使用経験があり、良い適応やあまり使用が推奨されない症例、長期成績、実際の手術手技の重要なポイントやピットフォールまで、実際の臨床例を交えながらの内容であった。今後始まる頚椎人工椎間板手術に関するOverviewとして大変ためになるセッションであった。
- その他:プロスポーツのACDF後の復帰時期や復帰率に関する発表があった。頚髄症JOA score及びその後発表された様々のmodified JOA scoreのReviewの発表があった。modified JOA scoreにはいくつかのVariationがあり、それぞれ少しずつ評価項目が異なるということは私は恥ずかしながら本発表で知り得た知見であった。
他大学の大先輩、同輩、後輩との懇親
会期中は日中の学会プログラム終了後、他大学の諸先輩方、同輩、後輩と夕食を共にして交流の機会を持つことができた (図5)。特に群馬の清水敬親先生と二晩にわたり、個人的に脊椎脊髄外科臨床医としての全般的な診療姿勢から、上位頚椎手術のピットフォールの詳細部分まで濃厚にお話しすることができたことは、私にとって本学会に参加したことで得たもう1つの大きな宝であった。
まとめ・おわりに
欧米にはTDRやACDFにおけるAllograft単独での固定など、本邦ではこれからようやく始まるものや、まだ未承認のもの、本邦ではまだ一般的でない治療法があり、彼ら発表から学ぶところも大いにある。しかしながら、我々は単に欧米の治療に迎合するのではなく、良い部分は取り入れつつも、日本の神経症候学を大切にする姿勢を大切にし、日本人・アジア人の文化、生活習慣を加味した我々の手術適応や治療ストラテジーを構築していくことが大切である。
最後に、日々お世話になっております大鳥精司教授、不在中業務を代行くださいました脊椎班諸先生方、研修医先生にこの場を借りて深謝申し上げます。