令和6年度教室例会開催のご報告
更新日 2024.12.18
同門会会員各位
拝啓
師走の候、先生方におかれましてはますます御健勝のことと御慶び申し上げます。
このたび、教室例会が盛会のうちに終了いたしましたことをご報告申し上げます。本年は全121演題のご発表があり、多岐にわたる斬新な研究成果や貴重な症例報告が共有され、極めて実り多い会となりました。多くの同門の先生方にご参加いただき、活発かつ建設的なご討議を通じて充実した学術交流の場となりましたことを、厚く御礼申し上げます。
また、忘年会におきましては160名を超える先生方にご参集いただき、久しぶりの再会を喜ぶ姿も見られ、和やかな雰囲気の中で有意義な情報交換の機会となりました。
なお、本年度の千整会奨励賞およびAward受賞の先生方より、受賞の声を頂きましたので、ここにご報告申し上げます。
来年度の教室例会は2025年12月12日(金)、13日(土)の開催を予定しております。来年度も数多くのご発表を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
敬具
各受賞者
2024年度千整会奨励賞(論文部門)
基礎部門:新井隆仁先生(平成27年卒)
「Osteogenic effects and safety of human induced pluripotent stem cell-derived megakaryocytes and platelets produced on a clinical scale」
この度は千整会奨励賞基礎部門に選出いただき大変光栄に存じます。
本研究は千葉大学イノベーション再生医学教室で行ったもので、私は2022年から2年間同教室に所属し基礎研究を指導していただきました。
近年、整形外科領域では多血小板血漿(PRP)の研究も進んでおりますが、PRPは患者因子の影響を大きく受けるため、効果が一定しないといった欠点があります。そこでPRPの代わりに、ヒトiPS細胞から作製した血小板による骨形成促進効果を検証するのが私の研究テーマでした。
近年、輸血など臨床で使用可能なスケールでiPS細胞由来血小板が生産可能となったことから、その血小板製剤もこれまでの実験室レベルで作成した血小板製剤と効果に差がないこと、またそれを実際にラットやウサギに投与することで有害事象なく骨形成を促進することを示した論文になります。
ご指導いただきました江藤浩之教授、高山直也准教授はじめイノベーション再生医学教室の皆様、実験や論文作成のアドバイスをいただいた志賀康浩先生、向井務晃先生、またこのような貴重な機会をくださった大鳥精司教授や整形外科の先生方にこの場をお借りして心より御礼申し上げます。
臨床部門:小林樹先生(平成28年卒)
「Study on ankle foot orthosis repair for patients with cerebral palsy」
この度は第9回千整会奨励賞臨床部門に選出していただき、誠にありがとうございます。このような栄誉ある賞を受賞できましたことを大変光栄に存じます。
本研究は、千葉県千葉リハビリテーションセンターの小児整形外科での勤務時に実施したものです。半年間に補装具外来を受診した脳性麻痺患者377名を対象とし、短下肢装具の修理原因について調査を行いました。32名に修理が必要となり、主な修理箇所は前足部の内側や外側に集中していました。この結果から、痙性を考慮した非荷重・荷重両面での評価、および実際の装着下での評価と経過観察の重要性が示唆されました。
脳性麻痺の療育と装具治療における定量的評価や統計学的有意差の検討は困難でしたが、英語論文として発表することができました。
鶴岡先生をはじめ、ご指導いただきました諸先生方のご支援により、この度の受賞に至りましたことを深く感謝申し上げます。また、装具作成にご尽力いただいた義肢装具士の方々をはじめ、コメディカルスタッフの皆様にも心より御礼申し上げます。
今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
若手部門:真秀俊成先生(令和5年卒)
「Incisura tangent method to determine the transsyndesmotic axis for
syndesmotic fixation」
この度は第9回千整会奨励症に選出していただき誠にありがとうございます。このような光栄な賞をいただき大変嬉しく思います。
本研究は足関節骨折に伴う遠位脛腓間離開に対する新たな固定方法であるincisura tangential technique(IT法)の妥当性について検討しております。
カルテ上の3D画像より模擬X線透視画像を作成しIT法を利用した固定法の軸と理想的な固定軸の角度差などについて調べました。
結果としてはIT法が遠位脛腓間離開の整復に有用な可能性が示唆されました。
本研究にあたり山口先生、木村先生、中嶋先生をはじめご指導いただいた先生方には多大なるご協力をいただき心より御礼申し上げます。
今後もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
千整会Award(発表部門)
基礎部門:柿沼康平先生(平成28年卒)
この度は整形外科例会において基礎部門Awardをいただき、誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。
本研究は、現在所属しております免疫発生学教室におけるご指導のもとで進めているものでございます。
全世界的にもCOVID-19のパンデミックが記憶に新しい中、感染症との闘いにおいてワクチンの開発および研究は引き続き重要な課題となっております。
その中でも今回発表させていただいた粘膜ワクチンは、千葉大学においてc-SIMVA(粘膜ワクチン研究開発拠点)が設立され、特に力を注いでいる分野です。
このような意義深い研究の一端を担えることを、大変光栄に感じております。
また、基礎研究における日常では、「科学的に興味深い論文をどのように作り上げるか」という視点で日々議論が交わされており、臨床とはまた異なる空気感の中で学ぶことができております。
こうした貴重な経験を積むことができておりますのも、整形外科の先生方のご支援とご厚意のおかげであり、深く感謝申し上げます。
今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
臨床部門:清水啓介先生(未来医療教育研究機構)
「交通事故後腰椎捻挫患者の長期通院を予測する要因~外力は一切関係がない~ 」
素晴らしい演題が多数ある中、伝統と栄誉ある賞に選出いただき光栄に存じます。本研究は「交通事故後腰椎捻挫の長期通院化予測」という、少子高齢化が進み社会保障費の逼迫が問題となっている本邦において大変重要な研究課題であると考えております。今回の研究は大阪行岡医療大学の三木先生のご協力のもと、損害保険料率算出機構より提供されたビッグデータを解析し長期通院のリスクファクターを特定しました。
結果として、重症例を除いて12週以上の治療に医学的、統計学的な意味はないことやドクターショッピングはかえって症状を遷延させること、心理ストレスや社会的困窮などが長期通院に寄与する因子であることが分かりました。今後の交通事故後の補償制度のあり方は今後も十分な議論が必要である結果となったと感じます。
本研究遂行にあたり御指導いただきました大鳥教授、稲毛先生をはじめサポートいただいております全ての先生、データ提供をいただきました大阪行岡医療大学の三木先生、バックアップいただいた日本痛み財団の先生に心より感謝申し上げます。今後も引き続き、研究成果を社会に還元できるよう取り組んで参ります。
若手部門:小澤元先生(令和3年卒)
「デノスマブ投与後に胸椎椎体骨折部の脊柱管内に異所性石灰化を生じた1例」
この度は、千葉医学会整形外科例会の若手部門Awardを受賞することができ大変光栄に存じます。
今回の発表は、慢性腎不全が背景にある患者様に骨粗鬆症治療薬であるデノスマブを投与後、脊柱管内に異所性石灰化を認めた症例についての発表でした。
デノスマブの副作用に低Ca血症が報告されていますが、慢性腎不全が背景にある場合、低Ca血症になりやすいとの報告があります。本症例でもデノスマブ投与後の低Ca血症を認めており、その際副甲状腺ホルモンの上昇を認めていたことから低Ca血症に起因した副甲状腺機能亢進による異所性石灰化の可能性があると考えました。
日常診療においても慢性腎不全の患者様にデノスマブを使用する機会は多く、血清Ca値を定期的にモニタリングする必要性を再認識した症例でした。
今回最初から最後まで熱心にご指導いただいた沖松翔先生、そして様々なご意見やご指導をいただいた成田赤十字病院整形外科の先生方にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。また、このような貴重な機会をくださいました大鳥精司教授、同門の先生方に心から感謝申し上げます。
今回の受賞を励みにより一層精進して参りますので、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
千葉大学大学院医学研究院整形外科学
教授 大鳥 精司
医局長 稲毛 一秀
事務担当代表 平沢 累
例会担当 眞木 成美


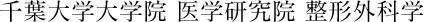

-750x1000.jpg)


